

なぜ過去に製作された映画を見ることができるのか
「みなさん、映像がない日常を想像できますか?」「過去に作られた映画をなぜ今も見ることができると思いますか?」セッション冒頭、水野より会場に問いが投げられました。
過去に作られた映像を今見るためには、映像を記録した“そのモノ(媒体)”が残っている必要があります。ただそれだけでは駄目で、例えば映画フィルムが残っていたとしても、再生する機材やフィルムや機材を扱える技術者がいなければ、映画を見ることはできません。何年も前に作られた映像を見ることができるのはなぜなのか、IMAGICAの歴史を振り返りながらトークが始まりました。

水野:
「IMAGICAは、映画フィルム現像・上映用のプリント事業を目的に、京都・太秦で創業しました。以来、87年間、映像作品の作り手であるさまざまな人たちと映像産業を築き上げてきました。そんなIMAGICAだからこそ、過去に製作した作品や現在製作中の作品を後世に残していく必要があり使命だと思っています」
フィルムそのものと技術をどのように伝承していくか――。「映像を未来へ繋ぐフィルム修復技術」を深掘るために、テーマを用意してセッションは進行していきます。
フィルムの「修復」とは?

ステージ上で柴田が手にしているのは、フィルムの缶。松尾から、フィルムから“映画の物量”に関して説明が始まりました。
柴田が手にしている缶は、1缶に1000フィート、約300m分のフィルムが入っています。このフィルムには、撮影して現像した画が約1万6000枚記録され、重量は約2キロ、1缶で記録できるのは約11分とされています。映画1本を110分とするとフィルムは10缶必要で、重さはトータルで20kg、長さは3kmにも。「これが130年ほど続いてきたフィルムの歴史です」と松尾は話します。
松尾:
「フィルムに限らず、世の中のものはどんなものも劣化します。フィルムは環境によっては手の施しようがないほど、劣化してしまう危険性を持ったものです」
フィルムの修復依頼は、映画会社や製作会社、テレビ局、美術館、企業、個人の方からなど、さまざまなところから依頼が入ります。「イマジカならなんとかなるかもしれない」とご相談いただくケースが国内外で非常に多いと言います。
デジタル保存とフィルム保存の違い
映像作品のデジタル保存とフィルム保存の違いについても話が及びました。
松尾:
「映画館からフィルムがなくなり、デジタルになりました。(フィルムの)修復作業をしているとフィルム至上主義のように思われますが、デジタルも本当に素晴らしいと感じています。フィルムは、1作品20kgもあり、ものすごい物量になりますが、デジタルは膨大なデータを保存することができます。活用しようと思ったらすぐにアクセスができ、離れた場所からでも見られるのはデジタルのメリットですね」
一方フィルムは、「物量としては大きいですが、保存性にとても優れています」と松尾。フィルムは現時点で130年残っており、劣化しているものもありますが、耐久性や保存性はデジタルよりも優位であるとされています。デジタルは、耐久性や保存性に対するリスクはまだあり、ハードウェアに依存しているためハードがなくなったら見られなくなる可能性もあります。また、データが消えてしまうといったリスクもあります。
松尾:
「ただ、デジタルの耐久性や優位性が解決されればフィルムがいらなくなるのかというと、またそこは違います。フィルム1缶には1万6000枚の画があり、これ自体にとても価値があります。それをどのように残していくかが課題だと思っています」

柴田は、フィルムの“劣化”について語ります。フィルムに付いた雪の結晶のようなカビを始め、写真を交えてさまざまなフィルムの状態を解説。
柴田:
「“劣化”と言っても、いろいろな症状があります。カビのほか、極端にパリパリに乾燥しているものもあれば、ドロドロに液状化しているもの、さまざまなパターンがあります。フィルムは機械にかけるため、物理的にダメージを負うことも多く、劣化だけではなく破損している場合もあります。修復の技術は、フィルム1本1本の症状に合わせ、お医者さんでいう処方箋(調査書)を書いて、治療(修復)方針をお客さんと検討する形で進めています」
フィルムに付着している汚れの結晶をクリーニング溶剤で落とすなど、フィルムの症状に合わせて直すため、技術者との間では「こんな機械があると復元しやすいよね」などと機械の開発についても会話がされるそう。
フィルムに色をつける「染色」の技術
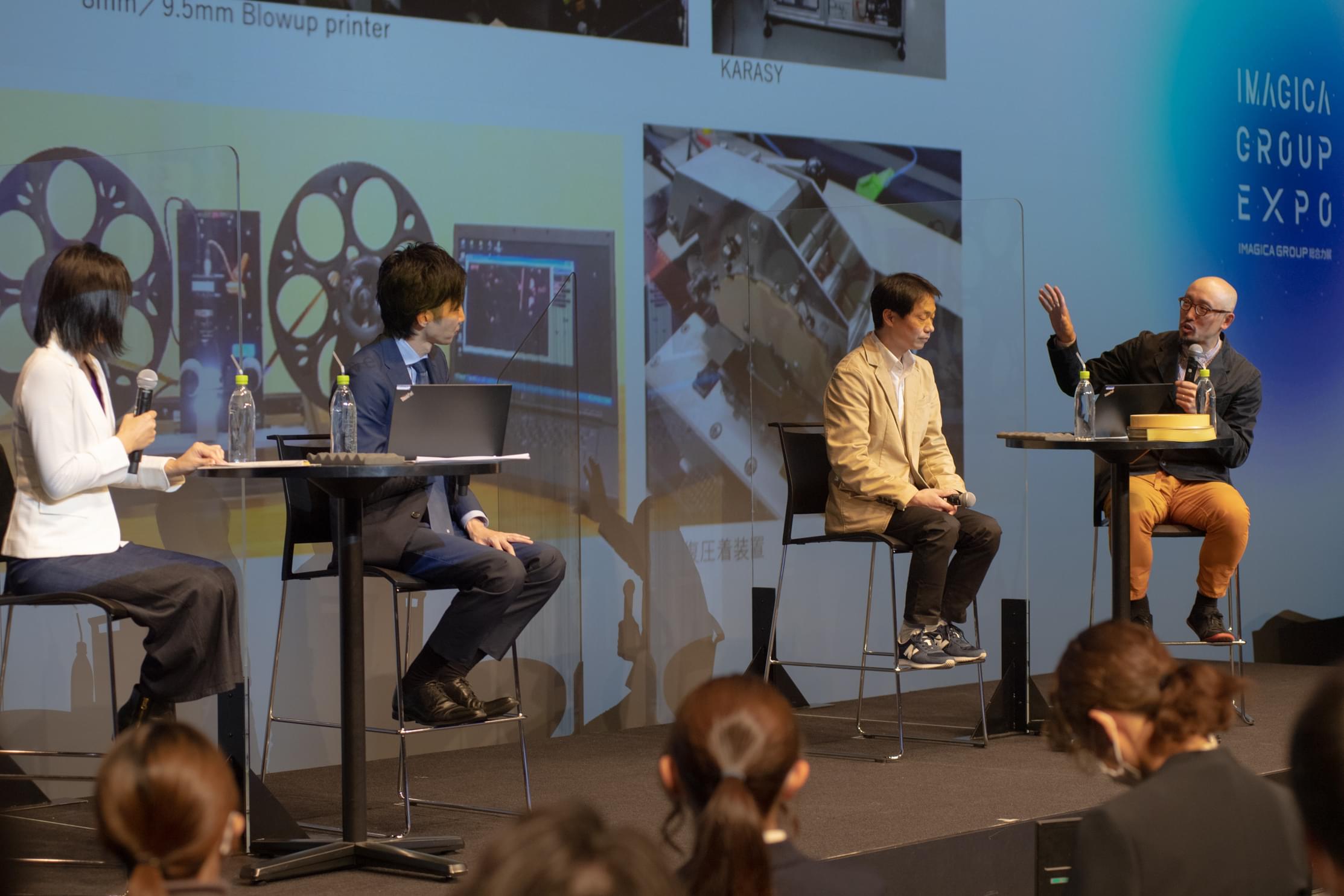
続いてセッションは「染色」の話題へ。
柴田:
「古い映画は白黒の印象がありますが、海外で古い作品を見た際、驚くことに、フィルム自体がとてもカラフルだったのです。サイレント映画で、フィルムに音がつく以前の作品で、映画の表現を豊かにするために、色彩で表現を補足していたということがわかりました。例えば、稲穂を入れるところを黄色に染めてみたり、ちょっと男女のロマンチックなシーンはピンクにしたり。フィルムで行われていた当時の染色作業も再現できないか、考えるようになりました」
フィルムだけではなく、当時の技術も含めて復元したいという思いから、染色の研究も始まりました。
水野:
「染色フィルムの色は何を基準に決めているのですか?」
柴田:
「フィルムにこそ痕跡が残っているだろうと考え、できるだけフィルムに残されたものに忠実であるように向き合っています。染料の濃いところは色を混ぜたのかな、などと、残っているものを一番の証拠と考え、フィルムが教えてくれる情報を忠実に再現するようにしています」
一方、松尾は、ミクロとマクロの視点を大切にしていると語ります。
松尾:
「私も10年以上前、染色を行っていました。当時はミクロの視点でフィルムを見ていましたが、当時の師匠が『フィルムを見るときは、ミクロの視点とマクロの視点の両方で見ることが大切』だと教えてくれたのです。色を再現する際は、ミクロの視点に加えて映画史というマクロの視点でも考え、100年ほど前の技術や道具を調べながら染色を行っています」
柴田は、当時の色を再現するために、技術も重要視しようと、現像機を転用した染色の機械を作りました。「フィルムを染料にドボンと浸けて引き上げたときや巻き取りの瞬間などは、どんなふうに色が出るかドキドキします」。
フィルムを未来につなぐために

フィルムそのものや関わる人、市場全体を通して、フィルムを未来につなぐために何が必要か、水野から問いかけがありました。
松尾:
「フィルムが映画館からなくなってしまった今、フィルムの市場は2つあります。1つは、新しいフィルムを使用する市場です。映像制作の中で表現として使いたいという作家や制作者がいますし、保存のために新しいフィルムを使用する場合もあります。もうひとつは、既存のフィルムを保存、活用していく市場です。130年の映画史の中で世界には膨大なフィルムが存在します。それらを保存、活用していくためにはフィルムの技術者が必要になります。しかし現在、世界的に現像所が少なくなり、修復技術を習得する場所はなかなかありません。しかし学びたい人は多く、ワークショップを開いて支援を行っています。フィルムの修復と合わせて技術者を育てていきたいと思っています。また、フィルムを使って映像の起源や原理を教えたり、絵を描いて映写したり、子どもたちにフィルム文化自体を広める活動もしています」
水野:
「こういった場で学んだ人たちが、50年後に今ある映像をどう残していこうか考える機会になるかもしれませんね」
松尾:
「フィルムはどうしても経年劣化してしまうので、技術者がいないとフィルムが残っていきません。しっかり残していくために人と技術は必要です」
柴田:
「発注者さんが社内を見学された際、若いスタッフが多いことにみなさん驚かれます。若い世代への技術のバトンタッチが着実に進んでいることを感じています」

最後に、今回の「映像を未来へ繋ぐフィルム修復技術」についてそれぞれが語りました。
松尾:
「今回、『映像を未来へ繋ぐ』という大きなテーマでお話をしましたが、私が携わっているのは、フィルムや映像を未来に繋ぐための本当にわずかな部分です。それ以上に、クライアントの方々が保存活動を続けていらっしゃることはとても大変なことだと思います。これからもフィルムの修復に少しでも力になり、継続していければいいなと思っています」
柴田:
「フィルムのさまざまな劣化の症状に対し、試行錯誤を重ねながら技術を磨いています。技術の向上によって救われるフィルムがあります。それを心に持ちながら仕事をしていきたいと、今日改めて思いました」
水野:
「本来であれば、技術者は作品に向き合えればいいはずですが、映像を未来に繋いでいくことを考えたとき、それだけではダメで、機材の維持や人材の育成も考えなければなりません。フィルムの修復は、改めて覚悟を持って取り組む必要があると感じています。ただ、私たちだけで取り組んでも、未来に継承することができません。みなさまとパートナーシップを築きながら映像文化の継承に取り組んでいきたいと思います」





